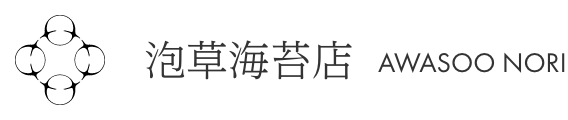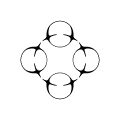海苔と秋の風物詩
台風21号の進路が心配される中、10月31日から11月1日にかけて、毎年秋に執り行われる海苔網の設置作業が行われました。私たちはその様子を見学させていただくため、いつもお世話になっている熊本県の河内町・松尾町を訪れました。皆さんが想像される海苔棚というのは真っ黒な網かと思いますが、それは海苔が付着し成長しているからであって、年に一度この時期だけは、真新しい色とりどりの網が海の上に広がるのを見ることができます。
網は31日の深夜のうちに沖に出て張ってくるとのことで、私たちは31日の昼過ぎから行われる予定の、網に牡蠣殻を取り付ける作業を見学し、翌1日の午後には、いつもお世話になっている松尾漁協のご厚意で船を出していただき、海上に張られた網の様子を見学させていただきました。
春、海苔の一年の始まり
海苔の成長の仕方をご存知の方はあまり多くはないかと思います。12月頃から始まり、翌年の3月頃まで続く収穫作業を終えると、まず海苔の胞子を<フリー>と呼ばれる状態に育てます。<フリー糸状態>というのが正式な名称で、海苔の胞子が枝のように糸を伸ばした状態です。広い桶に牡蠣殻を数枚ずつ糸で束ねたものを吊るして並べ、そこにフリーと海水を流し入れておきます。するとフリーは牡蠣殻の中に入り込んでいき、真っ白な牡蠣殻は海苔が入り込むことで色が黒っぽくなります。このようにして春から夏にかけて、海苔は牡蠣殻の中で成長をしていきます。

仕入れた時の牡蠣殻。小さな穴が開けられ、紐で繋がれている。

海苔網に取り付けられる直前の牡蠣殻。海苔が入り込み、全体に黒っぽくなっている。
この海苔の胞子が貝殻に入り込んで成長する性質を発見したのは、イギリスの藻類学者キャスリーン・メアリー・ドリュー=ベーカー氏です。この発見により、謎が多かった海苔の生活史の理解が深まり、日本の海苔の養殖業は飛躍的に向上・安定していきます。以前の記事でも書きましたが、このベイカー氏の顕彰碑が熊本県宇土市の住吉神社の境内にあり、そこで毎年<ドゥルー祭>という氏の功績を讃えるイベントが開かれるなど、とても大切にされています。
秋、海に広がる色鮮やかな海苔棚
水温が下がると海苔の胞子は牡蠣殻から出ていく習性があります。その習性を利用し、春から夏にかけて桶で育てたあと、秋になって海水温が下がると共に、牡蠣殻を網に取り付けて今度は海で育てていきます。殻から放出された海苔の胞子は網にくっついて育っていきます。海苔が放出された後の牡蠣殻は再び白い姿に戻ります。
1日目:牡蠣殻の取り付け(深夜に沖で網張り)
私たちが松尾町に到着した時は、ちょうど町の至るところで作業が始まった頃でした。そのうちの数カ所を回らせていただきましたが、網に牡蠣殻を取り付ける作業というのは「家族総出」という言葉がぴったりで、組合に所属している会社ごとに、老若男女が一緒に作業をしていました。時折談笑をしたり、歌を歌ったりしながらも、作業は忙しく進められていきます。
「きっとこの町の風物詩なのだろうなあ」
と思いを馳せないではいられませんでした。
やり方は大まかに二つの方法があるようでした。一つはロール状に巻かれた網が機械で回転し、それに牡蠣殻を取り付けていく方法で、もう一つは網を平面状に広げて積み上げたところに取り付けていく方法です。後者の方が網を広げて作業するぶん広いスペースを必要とします。こちらの場合でも、最終的には船に乗せるためにロール状に巻いていきます。
一方で共通しているのは、胞子を含んだ牡蠣殻を一つずつ袋に入れること。袋はお祭りの金魚掬いなどで使われるような大きさのもので、袋の中にはそれぞれ牡蠣殻が入っており(それと海水を入れるケースもあるようです)、それを手作業で網に括り付けていきます。そして括り付けの作業が終わると、ロール状に巻いた状態で作業船に載せて出航を待ちます。

ロール状に巻かれた網の前に並び、一つずつ手作業で袋に殻を入れていきます。

たっぷりと海苔の胞子が入り込んで真っ黒になった牡蠣殻。

牡蠣殻を入れてロール状に巻かれた網はトラックの荷台に積まれて港へ運ばれます。

港で網を広げて作業をしている様子。子供たちも網の上に乗って大人たちと一緒に作業に励みます。

ロール状に巻いて、作業船(四角船)に載せて沖に出ます。
2日目:沖での海苔網見学
午前中、天草にある水産試験場向けて車を走らせ、ほとんどピストンに近いような形で急いで戻っていく最中、宇土のあたりで作業中の漁師さんたちを車中から眺めることができました。まさに遠浅の海ならではの光景で、車が海の上を走り、漁師の方々も腰の辺りまで海に浸かりながら作業をしていました。朝から雨が降ったり止んだりしていましたが、寒い中作業をしている姿に自然と感謝の気持ちが湧き上がりました。


赤、緑、黄色、紫など色とりどりの網の間を、漁師の方々が歩いています。
待ち合わせ時間に近づくにつれて次第に雨は強くなり、私たちは急遽レインウェアを購入しました。そして集合場所に着くと、いよいよざあざあ降りで、船が出せるかどうかの心配もありましたが、それ以上に、取り付けたばかりの牡蠣殻や海苔は大丈夫なのだろうかと心配になりました。後に聞いた話では、雨は海水と異なるので困るが、多少海中が掻き回されるのはむしろ良いとのことで、それを聞いた時は少しほっとしました。
松尾漁協の組合長も到着し出航しました。船縁にしゃがんで捕まっていましたが、船の速度も相まって、雨が顔を容赦なく打ち付け、前を向いていられないほどでした。ようやく海苔棚に到着すると、波が荒れているのもあるのですが、ちょうど網に吊るした牡蠣殻が海に浸かったり、海上に現れたりするくらいの潮位でした。どんよりとした雨模様の中にあって、真新しい赤や緑の網はとても色鮮やかで、気分は少し晴れ晴れしてきます。さっそく網の近くまで船を寄せてもらいました。網にぶら下がった無数の袋をよく見てみると、深夜に網を設置してから海に浸かって海水が入っているのが分かります。



牡蠣殻から放出された胞子は海中を漂い、網に付着します。
ふと、この牡蠣殻はいつまで取り付けられているのだろうと疑問に思いました。河内漁協の参事の村田さんに伺ったところ、この牡蠣殻は早い人で当日から翌日、大体一週間ほどで取るとのことでした。思ったよりも早く取り外されることに正直驚いたのですが、その外す時の基準というのが、沖に張った網を1cmくらい切り取って持ち帰り、顕微鏡を使って海苔の胞子がどのくらい網にくっついているのかを確認して決めるとのことでした。つい自然と人とが織りなす素朴な営みばかりに目がいってしまうのですが、実際には自然の力と科学の力の両方を駆使して海苔業は行われているようでした。それがかえって海苔の不思議な生態を感じさせます。

微小な海苔の胞子を確認できる高性能な顕微鏡が並びます。
今はちょうど新海苔が美味しい季節です。胞子の状態から牡蠣殻を経て、あの美しい海で育て上げられた海苔とこうして東京で再会し、ようやく口にするのはとても感慨深く、一人でも多くの方にその喜びを共有できたら大変嬉しく思います。